本のキーワード
★悩みの答を外に求めない
悩みの答を外に求めない
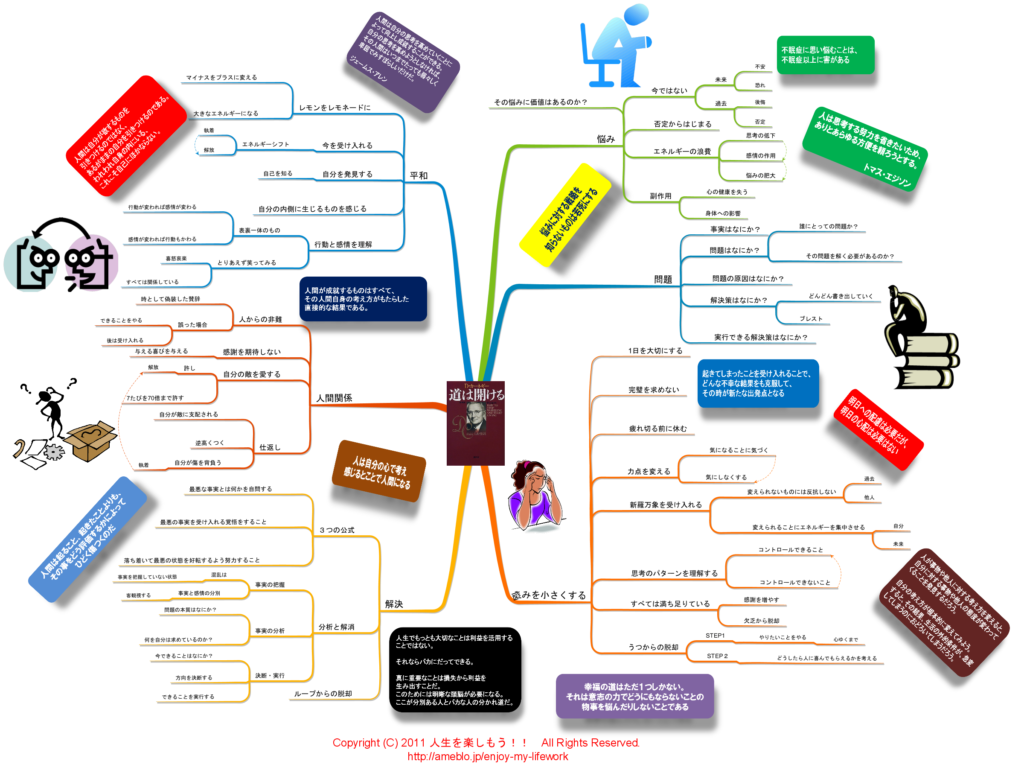
先日、自分の勉強のため、とあるグループカウンセリングに参加してきました。
カウンセラー1人に対してクライアント10人程度。
悩みを相談したいクライアントが、カウンセラーと1対1でセッションをして、短時間で悩みを解決していくというもので、他の参加者はそのやりとりを見ているというスタイルでした。
そこで強烈に感じたことが、クライアントはカウンセラーに「どうしたらいいでしょう~?」悩みの答を求め、カウンセラーはクライアントに「こうしたらいいよ~」と悩みの答を与えていました。
その関係性は依存関係に状態に陥っていました。
えっ?
なんでカウンセラーがクライアントの悩みに答えてはならないのですか?
と思われるかもしれません。
自分の中にあるルールブック。
そのルールブックには
・価値観
・固定観念
・思いグセ
・感情の発動条件
などなどがたくさん書かれています。
そして、人は自分のルールブックに反したとき、怒り、悲しみ、不安に感じたり、悩みを抱えてしまったりします。
そのルールブックはひとりひとりが違うもの。
だから、悩みもひとりひとりが違うもの。
僕がカウセリングをするときには、相手の悩みに対する答え伝える事は基本的にしません。
悩み自体を解決するための行動も要求しません。
というかできません。
なぜならば、クライアントのルールブックはクライアントにしかわからないから。
カウンセラーは、クライアント自身が自分のルールブックに気づいてもらい、クライアント自身がルールを取捨選択して、クライアント自身で行動を起こしていくようにサポートをするまでです。
先日のグループカウンセリングのカウンセラーの答は、カウンセラーのルールブックの答であり、クライアント自身の答ではないのです。
そして、クライアントがカウンセラーの答を日々の日常で実践したとき、”うまくいった”ときには、カウンセラーの答のおかげになり、”うまくいかなかった”ときには、カウンセラーの答の”せい”でこうなったという被害者意識を持つか、もしくは、もう1回答を教えてもらわなきゃという依存の関係に陥っていき、1番大事なクライアント自身の人生を自分の主体性を持って生きていくという大切さなことを奪ってしまうのです。
悩みに対する答を外側に求めるのは簡単なこと。
また、他人がその答を与えるのも簡単なこと。
でも、大事なことは、悩みは答えを外側に求めることではなく、なぜ自分がそのことに悩んだのか?ということを、深く感じることであり、時には苦しみながらも、悩みと向き合って解決した結果とそのプロセスに大切な答があるのです。
悩みは、今の自分の誤ったルールブックに気づくチャンス。
心の焦点を広げてから、悩みを感じてみましょう。
もちろん悩み苦しい時は人に相談してもかまいません。
でも、相談した結果の答は自分で決めるのです。
誰かから与えられた答では、自分自身の気づきや成長はなく、最悪、自分自身が主役の人生なのに、被害者の役を演じ続けなくてはならいから。
続きを明日書きます。
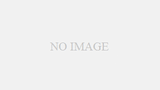
コメント