昨日の記事に続き。
自治会での防災訓練の中で、
今回、初めて炊き出し訓練を行った。
やはり3.11大震災の現実をみて、
実際に機材を使用する訓練をしなければ
意味がないという思いから、
子ども会の母親が炊き出しで食事を作り、
子ども達に食べさせるというものだった。
炊き出しのメニューは、
・ごはん
・ゆで卵
・ウインナー
・漬け物
・なめこの味噌汁
と炊き出しメニューとしては立派なものだった。
その食事を小学1年~6年生の約30名と一緒に、
公園にブルーシートをひいて食べたのだけど、
この時に1つ思った事があった。
それは、どんな時でも食事をおいしく食べられるという、
感覚がともて大切な事ということ。
自分も長男と一緒に食べていたのだけど、
何人の子どもから、
・ごはんが冷たくてまずい
・漬け物はきらい
・ゆで卵もきらい
そんな声が聞こえてきた。
そして、食事を食べ終えて
子ども達の包材を片付けているとき、
かなりの子ども達がごはんなどを残していた。
震災で炊き出しボランティアにいったのが5月。
とある地区の避難所では、
学校の体育館で数ヶ月生活をしていた。
当然、体育館には炊事をする場所もなく、
食事はすべて提供されるお弁当だけ。
そのお弁当は当然あたたかいものではない。
だから、自分たちが、あたたかいうどんを提供したとき、
避難所に居た方々はとてもよろこんでくれた。
もう1つの避難所の話。
そこは石巻市にある、とある女子校。
そこの学校も一部が避難所とされていて、
そこに居る方々に食事を提供した。
僕らの炊き出しメニューの中に、
ボイルウインナーがあった。
まあ、普通のウインナーをボイルしたものだけど、
自分がボイルウインナーを作っている最中に、
その学校の女子生徒達が近寄ってきて、
「ちょーうまそう~、震災以後、こういった普通のものが
食べられていないのです。もし避難所の方の食事が終わって、
ウインナーが残ったら、食べにきてもいいですか?」
みんな目をキラキラさせながら訴えかけてきた。
その学校がボランティア最終日とのこともあり、
少し食材も残っていたので、校長先生の配慮で、
生徒達にも食事を提供してあげて、
そのウインナーを訴えかけてきた生徒達も、
とても嬉しそうに普通のウインナーを食べていた。
自分にはこんな経験があるからか、
今回の自治会の炊き出しの残飯をみて、
少し残念な気持ちになった。
今の僕らの日本の社会では、食事を選択できる。
すきなもの・おいしいもの・手軽なもの・・
そのときの自分の状況に応じて、
食べたいものが食べられる。
それも今の日本の社会のすばらしい点だろう。
だけど、それは、
水・ガス・電気のライフラインが整い、
工場が稼働できて、お店が営業できる。
物資を配送するための道路が整備され、
トラックを動かすガソリンもある。
これらの要素がすべて満たされて、
はじめて成り立っている社会だったりする。
3.11の大震災のとき、
被災地は上記のすべてを失った。
その時から、あたたかい食事、
ウインナー1本すら食べる事が難しくなった。
そして、地震は次にどこで発生するかわからない。
もしかしたら、明日、関東で起きるかもしれない。
だからこそ、今回のような防災訓練が必要であり、
だからこそ、食事に対して好き嫌いを言うのではなく、
どんな食事でもおいしく食べる事が出来て、
その事に感謝できる感覚を日々訓練しておく
必要があるのではないか。
子ども達が残した残飯をみて、
そんな事を感じました。


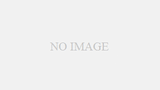
コメント