今回のキーワード
★お金とお米
お金とお米
以前の日本では、石高という単位で、土地の単位をみており、加賀100万石のように、国力を示すものでもあった。
では、1石とはどのような単位か?1石とは大人1人が1年間消費するお米を作れる土地の面積こと。
加賀100万石は、1年間に100万人の、お米を作れる土地があったということ。
また、その当時は、住民から徴収する税金も、兵士への給料もお金ではなく、お米でやりとりされていた。
どうして、当時はお金ではなくお米でやりとりをされていたのだろうか?
きっと、それは、お米は人が生きるために必要なエネルギーだから。
人がお米を作るのは、6ヶ月先の自らの命を継続させるために必要なエネルギーを作り出すため。
100万石の石高は、100万人分の人が1年間、生き続けられるエネルギーを生産できるということ。
以前の日本が石高を単位にしたのは、お米で利益を上げるためではなく、お米で多くの人の命を継続させることが、大前提にあったからだと思う。
いつからだろうか。
すべてがお金という価値の単位でやりとりされるようになったのは。
お金という価値は、今の社会文明のなかでは必要なものだけど、人と人が自然と共生して暮らすうえでは、あまり”価値”がないものなのかもしれない。
お金を田んぼに植えたところで、それが2000倍に育つことはない。
お金は人と人との間でしか育たない。
また、お金自体は生きるエネルギーにもならない。
でも、1粒のコメ(種)を田んぼに植えれば、それは2000倍にもなって育つ。
そして、それが自らの生きるエネルギーになる。
ただ、食欲を満たすための”お米”とみるのではなく、明日からも生きる続ける為に必要な”お米”と感じてみると、昔の人のお米に対する価値観が少しは感じられるのではと思います。
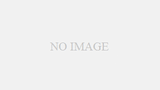
コメント