答えは自分の中にある。
それを質問より引き出せる。
問い塾で教わったこと。
それを、子どもとの関わりで実感出来ることがあった。
うちの長男は小学2年生。
先日、長男の宿題として、
「席替えの方法を考えよう」という席替えの方法を
自分で考えてまとめるものがあった。
その宿題の用紙には下記の3つの質問が書いてあり、
その下に長男の意見が書いてあった。
質問1:今回の席替えはどのような方法にしたいですか?
答え :好きな人と一緒のところに座ること。
質問2:その方法のいいところはどこですか?
答え :毎日、授業が楽しく受けられること。
質問3:その方法でうまくいかないところはどこですか?
答え :好きじゃない人と一緒になってしまうこと。
こんな感じの質問と答えだった。
そして、長男は質問3の答えで悩んでいて、
しばらくしたら自分のところに相談にきた。
「質問1で好きな人と一緒になると書いたのに、
質問3で好きじゃない人と一緒になると書いて、
なんだか、へんな感じがするのだけど。。。」
この相談を受けたときに、長男の質問3の答えは、
考えが1歩進んだ2次的な答えで、
本当の答えは1次的なところだと感じた。
それを、どう長男に教えるか?と考えたときに、
そうだ!!、
これも質問をして長男自身に気づいてもらおうと思い、
筆記用具とメモ用紙を長男に渡してから質問をしてみた。
質問:好きな人と一緒になる席替えなのに、
どうして好きじゃない人と一緒の席になるのかな?
答え:好きな人のところがもう座れないかもしれないから。
この時、長男に答えを1枚のメモ用紙に書かせ1番から番号をつける。
質問:どうして好きな人のところがもう座れないのかな?
答え:どこに座ろうかと悩んでいるとき、
既に好きな人のところがいっぱいだから。
質問:どうして、好きな人のところが
既にいっぱいになっているのかな?
答え:みんなが一斉に動いて近い人が早く移動できるから。
質問:どんなときに、みんなが一斉に動くのかな?
答え:先生が席替えを開始と言ったとき。
長男に4回質問を繰り返し、4枚のメモ用紙が書き出された。
そして、大きい数字の順からメモ用紙を並べて
書いたことを読んでごらん。
それが君が考えた本当の答えだよと教えてあげた。
この時、長男は「へっ??」ときょとんとした顔をしたけど、
自分が書いたメモを読んで「すごいー」と感心していた。
もちろん、自分も内心「質問はすごい」と感心した。
そして、長男の質問3の答えはこうなりました。
質問3:その方法でうまくいかないところはどこですか?
答え :先生が席替え開始と言ったとき、
みんなが一斉に動いて、
好きな人の周りがうまってしまい、
好きな人のところに座れないこと。
ほんと、質問により答えを引き出せるのだな~と実感をした。
そして、この宿題用紙自体が質問により構成されていて、
子ども達の意見を引き出すように作られている。
しかも、1つの方法の良いところ・悪いところと、
違った角度から物事を考えさせるようになっている。
小学2年生からこの考え方を教えてくれる
先生に感謝したい気持ちになりました。

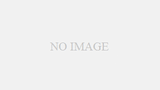
コメント