昨日の記事の続き。
なんとなく手にとった本をパラパラとめくって、
自分がその本を読みたいと思った動機を明確にする為に、
1つはマインドマップを使ってキーワード+体系に整理すること。
そして、もう1つが
上記で作ったマインドマップの情報から感じた事とを、
ブログに文書として表現すること。
自分のフォトリーディングの手順は下記のとおりです。
①本を選択。
②本をフォトリーディングする。
③本の内容を手書きマインドマップで作る。
④1週間ぐらい過ぎてから③のマインドマップを、
PC版のimindmapとして作りかえる。
⑤3週間ぐらい過ぎてから④のマインドマップをみて、
ブログの文書として表現をする。
②の本をフォトリーディングしてから、
⑤のブログとして文章にする為に
約1ヶ月間の期間をあけています。
それはなぜか?というと、
人の記憶の忘却曲線として、人は記憶したことの
約80%ぐらいを1ヶ月間で忘れるという。
それを逆手にとり、自分はあえて本で読んだ記憶を消してから、
マインドマップの情報だけで気になるキーワードやフレーズを基に
ブログの文章として表現している。
そうすることで、自分の本を読みたいという動機や、
その本から気づけた大切な事が明確にできるから。
先月、連続20冊ブログに書いてきた本は、
8月中旬~9月上旬にかけてフォトリーディングして
マインドマップの作成まで完了していた本。
10月になり、本の記憶を消してから、
20枚あるマインドマップから、
1枚をランダムに選択をして、
そのマインドマップを見ながら
感じることや思いつくことを
文書として書いています。
なので、
本の内容とブログ感想がだいぶかけ離れた文章になることが多い。
でも、そういう時の文章を書いているときは、
自分自身でで文章を書いている最中なのに、
「あ~なるほど~」と自分自身で気づく事がとても多い。
これはとても不思議な感覚。
もしかしたら、
これが「なんとなく手にとった」という事の
本質なのではと最近感じています。
1冊の本をフォトリーディングをして
マインドマップを作り、
それを基にブログに文書として表現をすること。
それだけでも、本の内容が自分の記憶として
定着していることをが実感できる。
そして、最近は上記+αの要素を取り入れている。
これがまたとても効果的な感じがする。
その+αの要素についてまた明日書きます。

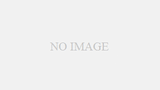
コメント