昨日の記事の続き、
竹の環境問題。
今回、竹藪の管理作業を行うにあたり、
竹の事を調べていたら、
竹に花が咲くことを初めて知った。
今伐採しているマダケは約120年に1回開花するという。
そして、その花に種を実らせて竹は一生終える。
この竹が自然の中で成長範囲を広げていくには、
根を地道に這わせていくか、
120年に1回の種を鳥などに運んでもらうかだけ。
でも、日本中に竹林があるのは、
人が竹の子とか竹製品を作るために、
人の手によって植えられたもの。
その当時は竹にメリットがあり、
人が管理を行ってきたのだけど、
メリットがなくなり高齢化が進み、
竹が放置されてしまっている。
僕が仕事しているオーナーが言うには、
「自然界の生態の中で、
1度でも人が手を加えたものは、
人が継続して管理していかなくてはならい。」とのこと。
人が自然界に手を入れるということは、
最初よりも、それを最後まで管理するということを
認識した上で行う必要があるのだと思う。
今の原子力発電所の問題も同じだと思う。
今、ニュースなどで、
原子力発電所の耐用年数の話をしているけど、
これだけ、原子力発電所が既に作られているのに、
どうして、今頃耐用年数の話をしているだろうか。
発電所の設計当時に耐用年数は考慮されていなかったのだろうか。
おそらく、原子力発電所は、
原子力発電所を建設して使う技術はあるけど、
原子力発電所を無くす技術はないのだと思う。
原子炉が稼働してしまった場所は、
原子炉の耐用年数が過ぎても、
もとの自然に戻すことはできないのだろう。
今僕らは、その原子力などの電力を受け、
安定して生活を送れている。
でも、数十年後の今の子ども達が大人になったとき、
耐用年数が過ぎた原子炉をどうするのか?
おそらく問題になっているのだと思う。
今僕が作業している竹林の問題のように。
その時のメリットだけを考え、
自然に手を入れるのは簡単。
でも、その最後にどう自然に戻すのか、
その事を考えないと、僕らの子ども達の世代に
ツケをまわすことになるのだと思う。

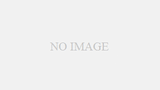
コメント