10/100冊目(去年累計61冊目)
【タイトル】
日本の田舎は宝の山
【著者】
曽根原久司
【本を読む目的・キーワード】
開墾の楽しさ
★人工密度の違い
都市農村交流事業とは
【感想】
この本の中で、
山梨県増富地区の事が出てくる。
山梨県増富地区は甲府の北側に
位置している山間にある、
とても景色がきれいな里山。
僕もバイクで何度も行ったことがある。
この増富は限界集落となっていて
増富は1万ヘクタールの広さに対して、
600人の住人しかいないとのこと。
ちなみに、
東京世田谷は6000ヘクタールに対して
100万人が住んでいるという。
1ヘクタール(100m四方の面積)に
約167人が住んでいる計算になる。
起伏が激しい山間の山里より、
平坦な関東平野に人が住むのは
あたりまえだとは思うけど、
都市に人が集中しているのだと思う。
いまある地方では過疎化になっている。
なぜ過疎化になってしまうのか?
恐らく、その地区で仕事がないからだと思う。
では、どうして仕事がないのか?
それは、2つの理由があると思う。
①.林業・農業などでは生活出来る収入にならない
②.仕事(サービス)を提供する人がいない
林業や農業、自然の相手のでは収入にならず、
地区に人がいないから仕事がなく、
仕事がないから人がいなくなる。
完全に悪循環に陥っているのだと思う。
この過疎化の問題を解決するのには、
①の事業で収入を得られるようにするか、
地区に人が来るような新たな3つめのモデルを構築して、
人が来るようになれば、②の仕事が成立してくると思う。
人が過密化する都心ではなく、
人が過疎化している農村に、
仕事を構築していくことが、
今の日本の理想だと思う。
日本の田舎は宝の山―農村起業のすすめ/曽根原 久司
¥1,680
Amazon.co.jp
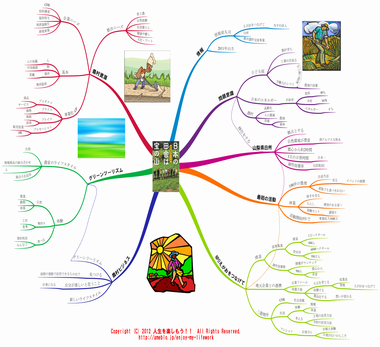

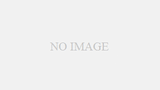
コメント
SECRET: 0
PASS:
林業が廃れてしまったからね。
日本の林業が、うまく活性化すると、もうすこし里山の若者の働き口ができるんじゃないかな。
働き口が出来ると、人が住まうから、経済も活性化するしね。
とにかく安いからといって、外材を輸入するというスタイルを、やめないとうまくいかないよね。
食材にしてもそうだけど、安いからという理由で購入するのは、どこか歪む。
購入根拠も生産方法も、「お金」中心になるからかな。
自然を相手にするものに対し、「お金」中心のサイクルがメインになってしまうと、やはりどこかおかしくなるように思う。
なぜなら、人は、自然と繋がれるけど、お金は自然とは繋がらないものなんだよね。
多くの人が、地球規模で何が今必要で、その中で、自分が何ができるのか?を いまひとつ考えてもらえたらな、と思う。
「お金」が欲しいから、という観点を少し離れてね。
うちも今、お金ものすごく無いから、でかいことは言えないんだけどね(笑)
SECRET: 0
PASS:
>空さん
そうだね~
お金自体には価値がなくて、
価値はその先にあるんだよね~。
だから、お金を中心にしてしまうと、
いろいろと歪みがでてくる。
お金は、その先にある価値を
じっくり考えてから使う必要がある。
これからの子ども達が
豊に生きていくためには
土台となる地球環境が必要で
その環境を維持することは、
とても価値があることだと思う。
まあ、僕もお金が無いから
えらそうな事は言えないけどね。
それでも、今は幸せだといえるから、
まあいいか(^O^)/
コメントありがとう。