33/100冊目(累計81冊目)
【タイトル】
会社組織が蘇る。職場系心理学
【著者】
監修:衛藤信之
作画:ナカタニD
【本を読む目的・キーワード】
心を学ぶことで
会社組織と成果主義
社内でのコミュニケーション
企業のメンタルヘルス対策
★交流分析
勝ちと負け
価値観の対立
3日の命
【感想】
昨日の記事の続き。
人は、過去の経験や、親との関わりにおいて
親の心(P),大人の心(A),子どもの心(C)、
この3+5キャラクター作られる。

基本的に、心の中には
この5つのキャラクターが全てが存在していて、
その時々のシチュエーションにより使い分けている。
また、その人の過去の経験などにより、
他より優位なキャラクターが存在している。
僕のエゴグラフの結果では、
NPとAC優位なキャラがいる。
どんな人にも3+5のキャラクターがある。
だから、今日出会う相手にも、
同じようなキャラクターがある。

そして、人はこのキャラクターを通して、
相手とコミュニケーションをしている。
そして、このキャラクターの違により、
コミュニケーションの受け止め方が異なってくる。
例えば、職場などで、
CP優位のきびしい”CP課長”
その部下に、AC優位のよい子の”AC君”と、
FC優位の自由奔放な”FC君”がいたとする。
CP課長がFC君とAC君を呼んで、
きびしい口調で、FC君とAC君の
仕事の指摘を始めました。
CP課長は同じ言葉で2人に指摘をしているのに、
FC君とAC君とでは受け止め方が異なる。
自由奔放なFC君は

FC君「課長また言っているよ~、とりあえず聴く振りをして、
それよりも今日ランチなにたべよう~」と
CP課長の言葉を心に入れないで、違う事を考えていたりする。
逆に、よいこのAC君は

AC君「課長にまた注意されてしまった。
自分はダメなんだ。どうして自分はダメなんだ・・・」と
CP課長の言葉を素直に心で聴いて自己否定につながったりする。
ここで大切なのは、FCが良くて、ACが悪いということでなく、
同じ言葉でも、キャラクターにより受け止め方が異なるということ。
そして、その事をCP課長が理解したうえで、
CP課長は、部下のキャラクターに合わせて、
時にはCPを使い、時にはNPを使い、
時には同じFCやACを使いながら
コミュニケーションを交わすようにする。
そのためにも、
CP課長は、自分自身のキャラクターと
相手のキャラクターを理解しておく必要がある。
続きを明日書きます。

マンガでわかる 会社組織が甦る! 職場系心理学 (じっぴコンパクト 62)/ナカタニD.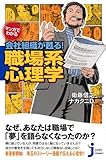
¥800
Amazon.co.jp

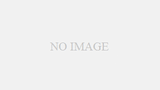
コメント